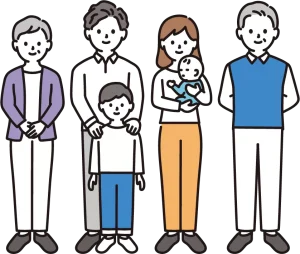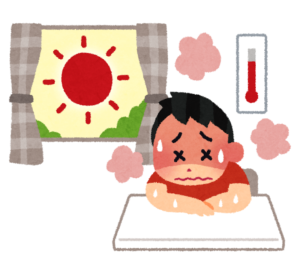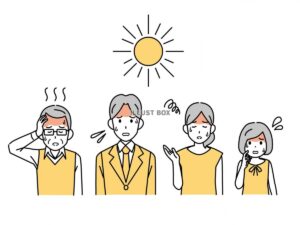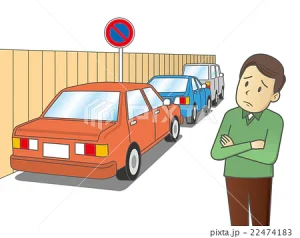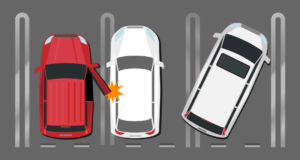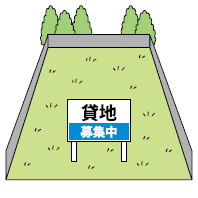不動産投資はやめとけと言われてしまう理由4つ|初心者が知っておくべき大切なこと
不動産投資に興味がある方、しようと考えている方は、
「不動産投資なんてやめとけ」「不動産投資ってなんか怖いよね」「難しそうだし、お金もないから無理でしょ」
などとネガティブな言葉をかけられたり、調べたらリスクや失敗ばかり出てきて戸惑ってしまうことも多いのではないでしょうか。
確かに、不動産投資にはやめておいた方がいい場合もありますし、投資なので当然リスクやデメリットもあります。
ただ、やめておいた方が良い場合を除き、不動産投資は堅実に資産形成ができる魅力的な投資法です。
当記事では不動産投資を「やめとけ」と言われる理由と、不動産投資は怖いものではないということ、逆にやめておいた方が良いパターンをご紹介します。
不動産投資に興味がある人から、やめといた方が良いと思っている人まで、ぜひご覧いただきたい内容です。
「不動産投資なんてやめとけ」と言われてしまう理由は主に4つあります。
- リスクが大きい割にリターン(利益)がそんなにない
- 空室が出てしまい、家賃収入が入ってこなくなる
- 不動産を借金をして購入しなければならない
- 物件管理の手間暇がかかる
ただし、やめとけと言う人の大半は先入観と思いこみで言っているパターンもあるため、果たして本当なのか?を考察していきましょう。
①リスクの割にリターンが低い
不動産投資を反対される1つ目の理由は「リスクが大きい割に利益がそんなに出ない」ということです。
確かにフルローンで不動産投資をする場合は、毎月入ってくる家賃収入から、ローン返済分や管理費など諸経費を引いた手残りは、毎月プラスになっていれば良い方。
例えば区分マンション(マンション一室)のキャッシュフローは、毎月1~2万円あればかなり良いでしょう。
確かに、不動産投資は短期的にみるとリターンは少なく、
1~2万円という数字だけ見ると、何百万、何千万の借金をして月1万…と肩を落としてしまう人もいるかもしれません。
ただ、不動産投資で利益を得る方法は家賃収入だけではなく、不動産を売却することでも可能。
数十年の長期間で投資金を回収しつつ、最終的に売却してより多くのキャッシュフローを得られる点は不動産投資のメリットです。
②空室で家賃収入が途絶える恐れがある
不動産を賃貸に出しても、入居者が退去してしまって、家賃収入がなくなってしまうのが怖いという人も多いです。
確かに、購入する物件選びに失敗したり、適切な管理が施されていなければ空室続きで家賃収入は得られなくなります。
「価格が安いから」「インターネットに書いてあったが高そうだったから」
など、安易な理由で物件を購入してしまうと、なかなか入居者がつかずに困ることもあるでしょう。
首都圏の駅近・周辺環境が充実している・ニーズに合っている(単身者向けかファミリー向けかなど)など、物件のポイントを押さえておき、
適切な管理さえしておけば、仮に空室が発生してもすぐに入居者はつきます。
③借金のリスクがある
借金をすること自体がリスクと考える人は非常に多いです。
住宅ローン・自動車ローンなどの必需品と違い、自分が使うものではないものにローンを組んで始めることを怖く思う気持ちは分かります。
収支計画もろくに練らずに無理に多額の借り入れをして不動産投資をした結果、失敗してしまう人がいるのも事実。
不動産投資の収支計画をしっかりと練り、年収・用意できる自己資金に見合った物件を選んでローンを組めば、怖いものではありません。
さらに住宅ローンや自動車ローンなどと違い、不動産投資のローン返済は自分が働いたお給料からではなく、入居者からの家賃収入で賄うことができるのです。
④投資物件の管理に時間・手間がかかる
不動産は所有しているだけでは家賃収入は得られないので、入居者募集や契約・対応、建物管理など管理業務を行う必要があります。
ただ、会社員として仕事をしながら管理業務なんてできるワケがない、手間や時間がかかるからやめとけ、と言われてしまう人もいるかもしれません。
確かに、管理業務時間も手間もかかるので、不労所得を得るとは言い難いでしょう。
ただ、管理会社に業務を委託することで、時間や手間をかけることなく不動産投資を行うことができるのです。
毎月の家賃収入の5%(管理会社)の管理費を払うだけで、入居者募集・対応(クレームや家賃集金など)・物件自体の管理清掃など一連の業務を任せることができるため、
自分ですることは管理会社から入ってくる家賃入金確認と、たまに来る管理会社からの報告の電話を受けるぐらいになります。
サラリーマンやOLでも不動産投資はできるのです。
2. 不動産投資は怖いものではない!初心者が理解しておくべき大切なこと
不動産投資はリスクが低く、安定している
不動産投資は多額の借金をするからリスクが高いと思われがちですが、株やFXなど他の投資と比べるとかなりの低リスクで行うことができます。
株やFXは値動きが激しいため、短期で一気に儲かる場合もありますが、一夜で暴落して何百万という損を出してしまうことも…。
一方で、不動産価格の値動きはゆっくりなので、一夜で急落したり、下がったとしても不動産の資産価値が0やマイナスになってしまうことはありません。
不況時でも賃貸需要は変化しにくい
人間にとって「住居」というのは生活を営むうえで必要不可欠のもの。
2008年のリーマンショック、2024年のコロナショックのような不況下でも家賃下落や、家賃収入がなくなったりすることはありません。
逆に不況下だと、住宅購入を考えている人も一旦踏みとどまって、賃貸に流れてくる可能性も高くなります。
入居者がいる限りは、不況下だとしても毎月安定した家賃収入を得続けることができるのです。
不動産投資のリスクと回避方法を知ることで失敗は防げる
不動産投資が低リスクでできることはお話ししましたが、投資なのでリスクはあります。
ただ、リスクの種類と回避・対策法があり、対策を講じておけば大半は回避できますし、万が一リスクが現実になってしまったとしても損失を最小限に抑えることができます。
簡潔に不動産投資のリスクと回避方法をご紹介しましょう。
| リスクの種類 |
概要 |
回避策例 |
| 空室リスク |
入居者が退去してしまい、家賃収入が途絶えてしまう |
- 需要のある立地や物件を購入する
- 適正な家賃設定をする(相場家賃を基準にする)
|
| 家賃滞納リスク |
入居者から家賃を滞納されてしまい、家賃収入が途絶えてしまう |
- 入居審査を厳しくする
- 管理会社や保証会社に依頼する
|
| 金利上昇リスク |
ローンの金利が借り入れ当初より上昇してしまい、返済額が上がってしまう |
- 固定金利を選択する
- 余裕があれば繰り上げ返済をする
|
| 災害リスク |
地震や火災などで建物に大きな損害を被ってしまう |
- 地盤が強いエリアや強い構造(RC・SRC)の物件を選ぶ
- 新耐震基準の物件を選ぶ
- 地震保険や火災保険に加入する
|
不動産投資すべてのリスクと回避策については以下の記事で解説していますので、参考にしてください。
不動産投資はやめておいた方が良い人の特徴

不動産投資はやめとけと言われるどころか、低リスクでリスク対策も明確、利回り計算もしやすいということがお分かりいただけたかと思います。
しかし、不動産投資は万人に向いているわけではなく、やめておいた方が良い人も存在するので、特徴をご紹介しましょう。
楽をして利益を出したい、リスクを一切取りたくない人
何もせずに楽をしてお金を稼ぎたい、リスクは一切取りたくないという人は不動産投資どころか、投資自体やめておいた方が良いです。
また、楽をして利益を出したいというのも投資では、ほぼ不可能です。
不動産投資ではある程度知識をつけてから、不動産会社や金融機関とのやり取りをして物件を購入、購入後も管理会社とのやり取りなど、さまざまな人とのやり取りが必要になります。
不動産投資についての勉強したくない人
不動産投資や不動産に関する勉強をしたくない人も、不動産投資はやめておくべきです。
儲かるという安易な理由だけで勉強を一切せずに始めると、利益が出る物件が何なのかもわかりませんし、不動産業者とのやり取りでも何を言っているか分からず、すべてを丸投げすることになります。
悪徳な不動産会社も存在するため、利益が全く見込めない物件を買わされて失敗してしまうということも…。
物件の善し悪しを見定められる程度の知識はつけておかないと、利益が出る不動産投資はできません。
投資金額を貯蓄できない人
貯金が全くない人も不動産投資にはおすすめできません。不動産価格の約20%は貯金がある状態が望ましいです。
確かに不動産投資はフルローン(不動産価格全てをローンで賄うこと)、つまり自己資金0円でも始めることが可能です。
しかし不動産投資を始めると、仲介手数料・ローン事務手数料・不動産取得税・固定資産税などの初期費用がかかってくることを忘れないでください。
また中古物件ではリフォームや修繕が必要になる場合もあるでしょう。
1年目は特にかかる費用も大きいので、貯金が0円、生活もギリギリというレベルで不動産投資を始めることはおすすめできません。
すぐに利益を確定したい人
上述したように、不動産投資は毎月少額でも安定した不労所得を得ていき、数年、数十年という長期目線で利益を確定させる投資法です。
短期で利益を確定させたい人には不動産投資は向きません。
不動産売買を繰り返してすぐに利益を得るという方法もありますが、2024年現在は不動産価格がすでに高値で推移しており、今後の不動産価格が値上がりすることはあまりないでしょう。
そのうえ、不動産の売却益に対しては「譲渡所得税」がかかり、5年未満の短期で不動産を売却すると39%と税率が高く、売買を繰り返して利益を得る投資法は難易度が非常に高くなります。
短期で利益を確定させたいなら、リスクを取ってでも株やFXなどの投資法を選びましょう
5. 不動産投資は投資手法を理解することで、やめとけと言われるような投資ではなくなる
不動産投資は、知識をつける、資金を準備するなどの事前準備をしっかりすること、またリスク対策を練ることで「やめとけ」と言われるような投資ではなくなります。
むしろ不況下でも安定した家賃収入を毎月生み出してくれ、低リスクでできる魅力あふれる投資法なのです。
短期で利益をたくさん得たい、楽をしてお金を稼ぎたいという人は、リスクは大きくなりますが不動産投資はやめておいた方が良いです。