空地の活用!資材置き場として募集をする際のメリットとデメリットは?

1.資材置場用地とは?
事業用賃貸での資材置場とはどういったものなのか。
過去に賃貸での募集をされたことのない貸主様は想像が難しいかもしれません。
資材置き場としての活用とは、基本的に土地をそのまま借主に貸して、「資材置き場」として利用してもらう方法です。
何を置くかは業種によって異なりますが、基本的にはその名の通り「資材」を保管します。
状況によっては、小さな建物やプレハブなどを置いて利用されることもあります。
「資材置場」とは、人が住む場所ではないので、どのような場所のどのような土地でも、需要さえあれば取り組むことが出来る土地活用法です。
2.空地を資材置場にするメリット
初期投資を低く抑えることが可能
土地の活用をする場合、建物などの建築に多額の費用が掛かることは当たり前です。
さらに、建物を建てるためにローンを組んだ場合など、長期間のスパンで返済をしていかなければなりません。
そんな中、入居者が途絶えてしまったりすると、ローンの返済が滞ったり、実生活まで締め付けることにもなりかねません。
しかし、「資材置場」として土地の活用をする場合、初期投資をかなり低く抑えることが可能です。
基本的には貸主様のほうでほとんど何もせずに引き渡すことが可能です。
状況によっては、多少の整地をしたり、防犯カメラの設置をすることもありますが、契約時に合意をすれば入居者に負担をしてもらうことも可能になります。
建物の建築等の初期投資が少ない分、その後の利益への転換時期も早くなります。
土地を管理しなくて済む
そもそも土地を所有していれば、その土地の管理をしなくてはなりません。
建築物が無ければそこまで頻繁に現地を確認する必要はありませんが、放置しすぎると不法投棄をされてしまったり、草木が生い茂ってしまったり、弊害が生じることがあります。
また、それが要因で近隣住民などに実害が発生してしまった場合、撤去を求められたり損害賠償をおこされてしまうケースも実際にはあります。
しかし、資材置き場として入居者に賃貸をしていれば、入居中の管理は基本的に入居者が行いますので、これらの時間と手間を省くことが可能になります。
簡単に更地に戻すことが出来る
建物が建築されている場合と異なり、「資材置場」としての賃貸であれば建物等を取り壊すことも必要なく、簡単に更地に戻すことが可能です。
建物がある場合、最初に建築や整地に要した初期投資分の回収が必要なため、簡単に賃貸をやめるわけにもいきません。
また、初期投資分を回収できたとしても、建物の解体にはそれなりの費用が掛かりますので、簡単に解体工事をすることも難しいのが現実です。
しかし、「資材置場」であれば更地に戻すということすら不要です。
賃貸が終了した段階で入居者からそのまま土地を返還されるため、所有者側で何かを施す必要は基本的にはありません。
勿論、イレギュラーなケースでは借主の残置した資材を片づけたり、プレハブを撤去したりという可能性はありますが、これも契約条項に入れて、借主側で対応してもらうことも可能です。
3.空地を資材置場にするデメリット
収益性が低い(賃料が安い)
「資材置場」としての賃貸の場合、初期投資を抑えている分、建物や駐車場での賃貸に比べて収益性は低くなります。
要するに、毎月所有者に入ってくる家賃が安い、ということです。
初期投資が低くて済む反面、こういった特徴があるので、双方の特徴を理解した上で検討をする必要があると思われます。
税金関連の軽減の恩恵が少ない
建物ありの賃貸に比べて、税金の軽減の恩恵が少ないことがデメリットになります。
具体的に言えば、固定資産税と都市計画税については住居用の建物が建っていないため、税金の軽減措置が受けられません。
また、居住用の建物が建っていないことで、小規模宅地の特例として相続税の軽減措置も受けられません。
あわせて、居住用の建物が建っていないことで借地権の設定が出来ず、その分の相続税の減税も認められません。
さらに、建物がないため建物に対しての減価償却も認められないので、その分を経費として計上し減税をしてもらうこともできません。
上記のように、デメリットの大半は税金関連になると理解をしておけばいいと思います。
4.土地活用のご相談は株式会社Y‘s upまで
ここまで「資材置場」としての土地活用について説明をさせて頂きました。
株式会社Y‘s upでは、事業用の資材置場としてお客様から多くのお問い合わせを頂いており、実際に使用をして頂いております。
お持ちの土地の活用をご検討の所有者様には、一度お問い合わせを頂ければ、その物件に合うお客様をご紹介させて頂きます。
土地活用をお考えであれば、株式会社Y‘s upまでお問い合わせください。




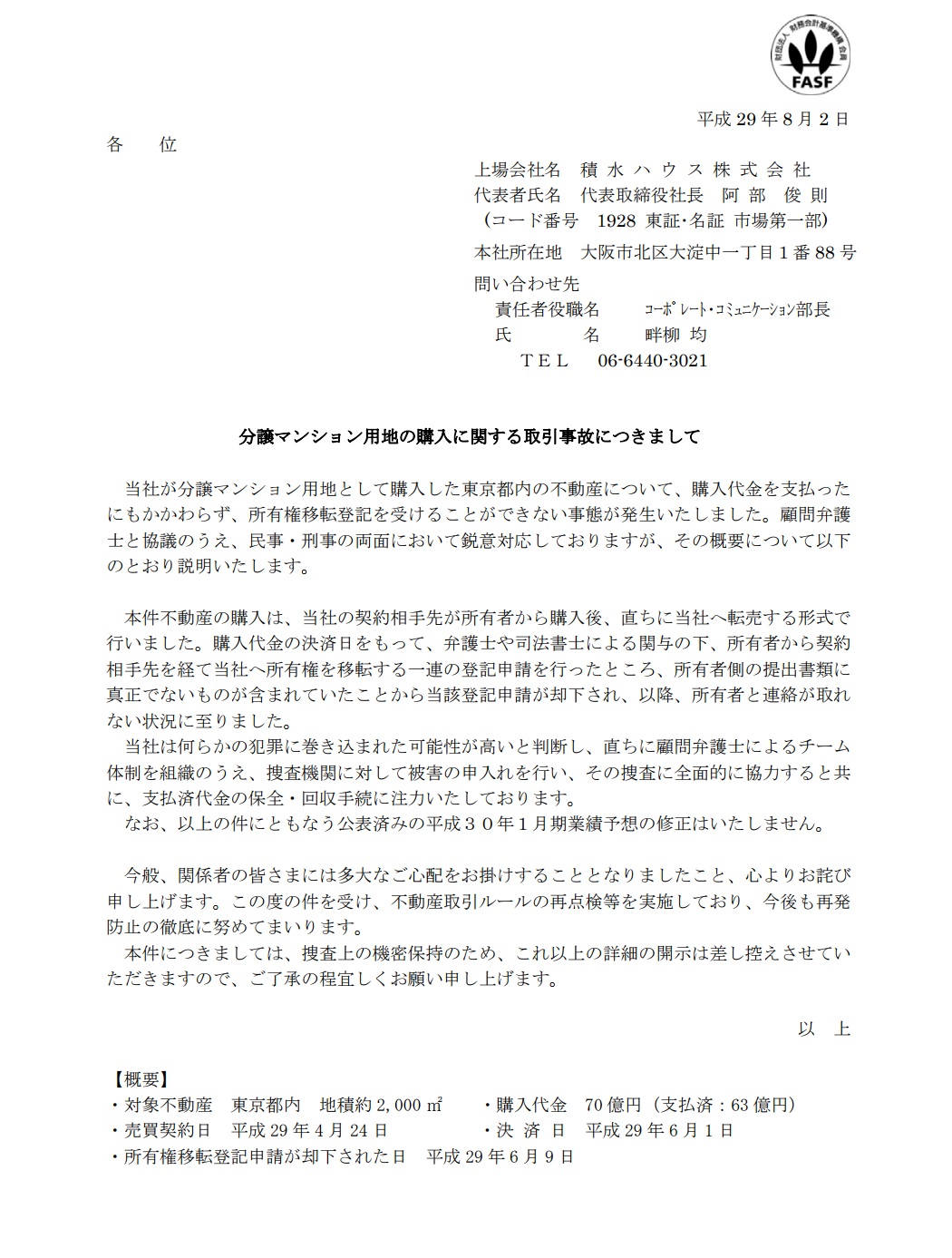

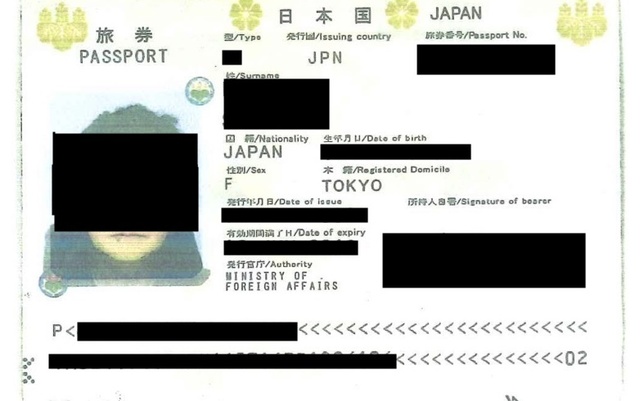
![住みたい街(駅)ランキング[1位~10位]](https://suumo.jp/journal/wp/wp-content/uploads/2024/02/201057_sub01.jpg)





