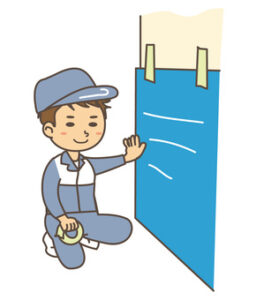外装塗装を梅雨の時期にしても大丈夫なのか?
そんな疑問にお答えします。
外装塗装を決めた方は、次に具体的に時期や費用を考えるのではないでしょうか?
時期は、一時的に春、秋がいいといわれています。実際に業者に梅雨時期である6月ごろを提案された場合、皆様はどのような印象を持ちますか?
梅雨時期は、地域にもよりますが週3~5日雨が降ることがあります。
外装塗装を雨の多い時期にしてもいいにだろうか。とお考えになる方もいます。
しかし実は、梅雨時期でも注意をすれば外装塗装をすることができます。
梅雨の時期でも外装塗装はできる!!
塗装は1年間通して行うことができます。塗装メーカーの出している基準では、
湿度:85%未満
気温:5℃以上
天候:晴れまたは曇り
の、環境元であれば塗装が可能なため条件を満たしていれば1年間通して塗装が可能になります。
先進の塗料技術と適切な工程管理にあります。現在市場に出ている多くの塗料は、湿度が高い状況下でも効果的に機能するように設計されています。
これらの塗料は、湿度が塗膜の硬化を妨げるのを防ぐ特性を持っているため、梅雨時期でも使用することが可能です。
さらに、塗装業者は天気予報を密にチェックし、雨の予報がない日を見極めて塗装作業を行います。また、急な天候の変化にも対応できるように、
作業の段取りを柔軟に変更できる計画性も重要です。
雨時期の外壁塗装のメリットとは?
一見、梅雨時期の外壁塗装はリスクが伴うように思えますが、実はこの時期ならではのメリットがあります。
多くの人が避けるため、業者の予約が取りやすくなるのはもちろん、競争が少ないため価格交渉がしやすく、割安で工事を行える可能性が高まります。
これらのメリットを活かすことで、賢く外壁塗装を行うことが可能になります。
注意点とデメリット
梅雨時期の外壁塗装にはメリットが多い一方で、いくつかの注意点とデメリットが存在します。
最も顕著なのは、予測不可能な天候による工期の延長リスクです。
さらに、高湿度が原因で塗料の乾燥に時間がかかることがあり、これが仕上がりの質に影響を及ぼす可能性があります。
これらのリスクを理解し、適切に対処することが重要です。
工期の延長リスク
梅雨時期は予期せぬ雨が降ることが多く、これが直接的に工期の延長につながります。
予定していた作業が行えない日が出てくると、結果的に全体のスケジュールに遅れが生じる可能性があります。
このような状況を避けるためには、業者との密なコミュニケーションが必要です。
梅雨時期の外壁塗装を成功させるポイント
工事スケジュールの調整方法
梅雨時期に外壁塗装を行う最大の課題は、変わりやすい天候に対応することです。工事スケジュールを柔軟に調整できるよう、業者と密接に連携を取り合うことが重要です。
事前に「雨天時の代替計画」を確認し、天気予報に基づいて作業日を決定します。また、突然の天候変化にも迅速に対応できるよう、日々のコミュニケーションを欠かさないことが必要です。
業者選びのコツとアフターケア
梅雨時期の外壁塗装を成功させるためには、経験豊富で信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。
業者選びの際には、過去の施工事例や顧客の口コミを確認し、梅雨時期の塗装経験が豊富な業者を選ぶようにしましょう。
また、施工後のアフターケアや保証についても事前に確認しておくことで、将来的なトラブルを避けることができます。
梅雨時期の外壁塗装は、適切な準備と対策を行うことで、通常時と変わらぬ品質の仕上がりを実現することが可能です。
業者との良好な関係を築き、細やかな計画と柔軟な対応で、雨の多い季節も乗り越えましょう。