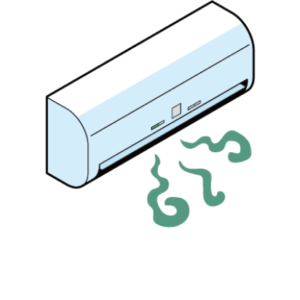施工管理と現場監督の違い

冒頭でも述べた通り、施工管理と現場監督に大きな違いはありません。
ただ、現場監督が作業員への指示や資材の発注など、現場での仕事が多い一方で、施工管理は現場以外にも「事務作業」「クライアントとのやり取り」などの作業もおこないます。
つまり、施工管理と現場監督の違いを強いて挙げるとするならば「業務内容」「業務の幅」にあると言えるでしょう。
逆に共通するポイントとしては「現場のスケジュール管理をおこなう」「現場の職人や作業員に指示を出す」などがあります。
施工管理も現場監督も未経験OK
施工管理と現場監督は、未経験でも十分に目指せます。実際、未経験者でも積極的に受け入れてくれる会社は多いです。
しかし、施工管理と現場監督は、現場全体を指揮したり、豊富な知識を持つ職人とコミュニケーションをとったりする必要があるため、十分な専門知識とスキルを要します。そのため、未経験からのチャレンジは正直なところ難易度は高いです。
とはいえ、施工管理で必要なスキルや知識は、現場で経験を積めば誰でも習得が可能なため、難しく考える必要はありません。
「施工管理を目指したい」「現場監督になりたい」という人は、まず仕事内容について理解することから始めるとよいです。
施工管理(現場監督)の仕事内容

施工管理(現場監督)の仕事内容は下記の通りです。
- スケジュール作成
- 現場の調整
- 予算の管理
- 現場の雰囲気づくり
- 安全管理
- 事務管理
それぞれの仕事内容について分かりやすく解説します。
1.スケジュール作成
スケジュールの作成は、建設現場で最も重要視されている仕事となっています。スケジュール通りに工事を進め、工期内に現場を完成させることは「顧客の信頼アップ」「コストの削減」などにつながるためです。
そのため、施工管理は、効率的かつ無理のない工期スケジュールを作成しなければなりません。
具体的には「週間工程」「月間工程」「全体工程」という段階ごとのスケジュールを組んだうえで定期的に打ち合わせなどをおこない、工期までに現場を完成させます。
2.現場の調整
施工管理と現場監督は、現場を完成させるために必要な機材・材料、人員などの調整もおこないます。
建設現場では、悪天候や作業ロスなどによるトラブルが付きものですから、施工管理は常に、人員や機材を調整します。
加えて、安全な作業に必要な機材や人員を確保することも大切な仕事の一つです。H3 3.予算の管理
決められた予算の中に収まるように工事の進行を管理するのも施工管理の仕事です。
たとえば、作業の進捗が遅れている場合「人件費」「機材のレンタル費」などの経費が追加で必要になります。そういった追加の経費が予算内に収まるかどうかを判断したり、調節したりするのが主な仕事です。
また、現場でかかる費用とは別に、会社運営にかかる「減価償却費」「維持費」などは一般管理と呼ばれ、会社によっては施工管理が管理をおこないます。
4.現場の雰囲気づくり
現場では、職種の異なる大勢の人が関わり合いながら仕事を進めています。一人ひとりが異なる価値観を持ち、任命された仕事を遂行しているのは建設現場ならではの特徴でしょう。
そんな多様な考えをもった人が大勢いる現場で、円滑に工事を進めるために必要なのが「雰囲気づくり」です。
普段からさまざまな人とコミュニケーションをとり、信頼関係を深めることで工事がスムーズに進みやすくなります。命の危険と隣り合わせでもある現場では、必要不可欠な仕事の一つと言えるでしょう。
5.安全管理
現場には人より大きい重機や高所など、命に関わるような危険が数多く潜んでいます。現場監督や施工管理は、こういった危険から作業員を守らなければなりません。現場を指揮する人にとっては非常に大切なミッションと言えるでしょう。
たとえ工期内に現場を完成させたとしても、重大なケガ人を出してしまうと「業務クオリティが低い」とみなされます。
危険から身を守るためのルールは各現場によってすでに設定されているため、施工管理や現場監督はそのルールを遵守させることが主な業務です。現場で働いている人に危険が及ばぬよう、安全に配慮した指示を常に出していく必要があります。
6.事務作業
現場全体を任されている施工管理は、事務作業もおこないます。
具体的な業務内容は、
- 施工プランの作成
- 施工計画に関する書類の作成
- 工期スケジュールの作成
- スケジュール管理の調整
などと多岐にわたります。
また、現場が完成したあとも「安全確認の書類」「報告書」など、作成しなければならない書類は非常に多いです。
ちなみに「事務作業は施工管理がやるもの」というイメージが強いですが、現場監督も図面を描いたり、写真を整理したりなどといったデスクワークがあります。
施工管理(現場監督)の年収

建設業界全体の平均年収の推移を平成20年~26年で見てみると、400~415万円の間を横ばいに伸びていることが分かります。
一方、転職エージェントdodaのデータを見ると、施工管理の平均年収は444.3万円でした。
このことから、施工管理の平均年収は、建設業界の中でも比較的高いことが分かります。年収の差にして40万円ほど変わるため、決してその差は小さくはないでしょう。
また、建設業界の平均年収がほぼ横ばいであることから、業界内の年収は「上がりにくく下がりにくい」という特徴を持っていることが分かります。
年収を上げる方法
年収を上げる主な方法は「施工管理技士の資格を取得する」「経験を積む」の2つです。
最もイメージしやすいのは資格の取得でしょう。施工管理技士を取得することで会社から「十分な経験と知識を持っている」と判断されるため、転職直後でも高い給与を得られます。
また、経験を積むことも年収を上げるうえで大切な要素です。
「どういった立場で何年間の業務を全うしたか」という点は転職面接の際などに必ず見られます。十分な経験があると判断されれば、転職に伴って年収を上げることも可能です。
経験の有無を分かりやすくアピールするために作られたのが施工管理技士の資格ですから、年収アップを目指したい人は勉強をしてみるとよいでしょう。
まとめ
本記事では「施工管理と現場監督の違い」「施工管理’(現場監督)仕事内容」などを紹介しました。
施工管理と現場監督の仕事内容には、あまり大きな違いがありません。強いて言うのであれば「業務範囲の広さ」です。
現場をメインとした現場監督の仕事よりも、現場と現場外の仕事を請け負う施工管理のほうが業務範囲が広いのです。
また、施工管理も現場監督も未経験から挑戦できます。ただ本記事で紹介した通り、たくさんの経験や知識を要するため、まずは現場での実務経験を積むことが大切です。










 地震に強いのはどんな屋根?
地震に強いのはどんな屋根?