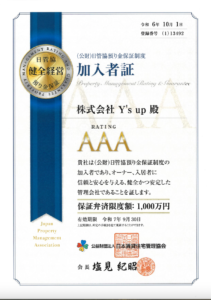DIYで断熱性能を高められるアイテム、どんなものがある?
CAINZをはじめ、ホームセンターでは、DIYで断熱や結露対策できるアイテムを多数、開発・販売しています。DIYというと、のこぎりで材料を切ったり、ビス打ちをしたりと、手間がかかるイメージがあるかもしれませんが、CAINZで扱っているアイテムの多くが特別な道具を用いずに施工できるそうです。
断熱DIYアイテム① 窓ガラスに貼るタイプの「断熱シート」
中でも、窓ガラスに貼るタイプの断熱シートは施工性が高く、効果も高いといいます。
「水で濡らして貼るタイプとシールになっているタイプがありますが、いずれも緩衝材のように空気を含んでいるシートになっています。窓のサイズに合わせてハサミでカットできるので、DIY初心者の方にも扱いやすいと思います。キャラクターが描かれたものや柄が入っているものもあるので、場所や好みに合わせて選べます」(宮田さん、以下同)
■カインズ 水貼り断熱シート 窓ガラス用 幅90cm×長さ180cm 2巻パック 998円
※商品の金額は取材当時のものです(他同)

空気層の効果で窓ガラスの熱の伝わりを小さくし、冷暖房効果を高める(画像出典:CAINZ)
経済産業省資源エネルギー庁によれば、住まいの断熱で重要なのが、窓などの開口部です。冬の暖房時に熱が流失するうち開口部からの割合は58%、夏の冷房時に熱が入るうち開口部からの割合は73%というデータもあります。開口部とは玄関、窓、換気口など。その多くを占める窓の断熱性能を高めることで、夏も冬も冷暖房効率が良くなり、快適に過ごすことができます。

(出典:経済産業省 資源エネルギー庁)
CAINZで扱っている窓に貼る断熱シートは簡単に剝がせるため、賃貸住宅の窓にも貼ることができます。価格も500円~2,000円程度と安価なので、部屋ごとに貼り替えてお部屋の印象を変えてみるのもいいかもしれませんね。
「窓の断熱性に加え結露に悩まされている場合は、吸水できるタイプがおすすめです。結露を放置してしまうと、カビの原因になってしまいます。かといって、毎回、拭くのも大変です。結露吸水パネルは、断熱効果も防カビ機能も備わっています」
■カインズ 断熱効果のある結露吸水パネル ブラウン 60×90cm 998円

窓ガラスに貼って結露水を吸収する(画像出典:CAINZ)
断熱DIYアイテム② カーテンレールに取り付ける「断熱カーテンライナー」
窓の断熱性を高められるアイテムは、断熱シートだけではありません。「断熱カーテンライナー」は、窓ではなく、カーテンレールに取り付ける断熱アイテム。床の上に引きずるように窓とカーテンの間に垂らすことで、熱気・冷気の侵入となる隙間を防ぎます。
「カーテンレールに引っかけるだけなので、断熱シートを貼るより簡単かもしれません。冷たい空気は重く、下に貯まりやすいのですが、このカーテンライナーは一般的なカーテンより裾が長くなっているため、まるで部屋を包んでいるような状態になり外からの冷気が窓の下部から入ってくることもありません。冷暖房両方の効率が上がるため、季節問わず人気の商品です」
裾や幅が長すぎる場合は、ハサミやカッターで簡単にカットできます。光を通すタイプのカーテンライナーも販売されています。
■断熱カーテンライナー 150×225cm 2枚入り(Sカン18個入) 1,680円

窓やカーテンのすきまからの熱気・冷気の侵入を遮り、室内の熱気・冷気を逃がさない(画像出典:CAINZ)
断熱DIYアイテム③ サッシやドアの隙間を埋める「すき間テープ」
開口部の熱の流出が大きい理由は、熱伝導率が高いことに加え、隙間があるからです。わずかでも隙間があると、そこから熱が逃げ、室内の温度が一定に保たれにくくなってしまいます。そこでおすすめなのが、サッシやドアなどの隙間を埋められるテープ。施工性が高く、効果も大きいといいます。
「断熱シートやカーテンライナーとあわせて使っていただくことで、断熱効果はかなり高まると思います。ここまでご紹介した商品はどれも簡単に施工できるので、ぜひ試していただきたいですね」
■カインズ すき間テープ グレー 幅30mm×長さ4m 厚さ10mm 248円

ウレタンスポンジによりすき間風をブロック(画像出典:CAINZ)
断熱DIYアイテム④ 窓断熱性能が2倍以上に!?「内窓キット」
少し上級者向けのアイテムとして「内窓キット」もご紹介いただきました。内窓とは、既存の窓の内側に設ける窓。窓を二重にすることで、断熱性・気密性が高まり、部屋の中の温度を一定に保ちやすくなります。
「CAINZでは、別売りのパネルと組み合わせて施工する内窓フレームキットを扱っています。フレームやパネルを窓の大きさに合わせてカットしたり、ゴムハンマーなどを使ってパネルにフレームを取り付たりする工程は必要ですが、内窓を取り付けていただくことで窓断熱性能は2倍以上に向上(室外温度0℃・室内温度20℃・ガラス単板アルミサッシを想定)し、冷暖房効率も高まります」
■小窓用キット ホワイト PTWーA 4,980円

窓を二重構造にすることで、断熱性アップ・冷暖房効率アップ・結露抑制に期待できる(フレーム内に入れるプラスチック板は別売り)(画像出典:CAINZ)

(画像出典:CAINZ)
ほかにも、「カインズ中窓用フレームキット」5,980円、「カインズ大窓用フレームキット」8,480円(別売のポリカボード2,580円(すべて税込)も必要)があります。
■関連記事:
【断熱DIY】ホームセンター商品だけで賃貸の部屋も夏涼しく・冬暖かくできる! 原状回復OK、内窓・玄関ドア・床などをひと部屋4万円以下で
より本格的?!「内窓フレームキット」を使って実際にDIYしてみた
ホームセンター各社では断熱アイテムの開発・販売がされていますが、CAINZでは自治体や専門家と一緒に断熱ワークショップを開催しているといいます。
2025年2月には、CAINZ本庄早稲田店で、埼玉県主催の「家庭の省エネ実践講座」が開催されました。同講座では、専門家による断熱セミナーの後、内窓DIYワークショップを実施。筆者も小学生の娘たちと参加し、CAINZのスタッフや専門家の指導のもと、内窓フレームキットを使って実際にDIYしてみました。

埼玉県地球温暖化防止活動推進センターの秋元智子(あきもと・ともこ)氏による断熱セミナーの様子(写真撮影/亀梨奈美)
まずは、用意された木枠を窓枠に見立て、メジャーで寸法を測ります。続いて、キットに入っている塩化ビニル樹脂のフレームを計測した長さに合わせて切断します。これが内窓の枠となります。切断に使うのは、プラスチック専用のこぎりです。「まず印を付けた場所にのこぎりで傷をつけ、刃が入りやすくするのがコツ」とスタッフの方が教えてくれました。

窓枠を採寸し、フレームをのこぎりでカット(写真撮影/亀梨奈美)
のこぎりで切っただけでは切断面がギザギザなため、やすりで綺麗にします。フレームを組み合わせたときに隙間が生じないようにするためにも、ここで綺麗にしておくことが大切です。完成した後の見た目も良くなります。

フレームの切断面をやすりで綺麗にする。やすりがけなら低学年の子もお手伝いできそう(写真撮影/亀梨奈美)
引き違い窓の場合、切断するフレームは、2つの窓の四隅+窓枠の四隅に取り付けるため計12個。同じ作業を繰り返していくうちに、切断・やすりの工程にも馴れてきました。
続いて、内窓の窓面になるパネルを切断します。内窓フレームキットにはパネルは含まれておらず、別売りです。ここでは、断熱性が高い「ポリカ中空ボード」と呼ばれるパネルを使用しています。やや厚みはありますが、カッターで切断可能です。

パネルをカッターで切断。厚みがあるので何度か刃を入れる必要がある(写真撮影/亀梨奈美)
切断したフレームを、窓枠に見立てた木枠に両面テープで貼り付けていきます。上下のフレームは、窓をスライドできるようレールになっています。切断したパネルにも、フレームを取り付けます。パネルの枠となるフレームはコの字になっているため、パネルを挟み込む形です。ハンマーで軽く叩くと、ピッタリはまります。

窓枠、パネルにフレームを取り付ける(写真撮影/亀梨奈美)
あとは、フレームを付けたパネルを窓枠にはめるだけ。これで完成です。

完成した内窓(写真撮影/亀梨奈美)
使用した工具は、メジャー・プラスチック専用のこぎり・金属製やすり・カッター・ハンマー・両面テープ。子どもと一緒につくったため完成までに1時間半ほどかかりましたが、大人だけであれば1時間かからずDIYできそうです。
キットを使った内窓のDIYは、貼るだけの断熱シートやすき間テープと比べると時間も手間もかかるため、宮田さんの言うように少し上級者向けかもしれません。ただ、作る過程も楽しむことができ、時間をかけてつくったものには一層、愛着がわくはずです。
断熱アイテムと需要の変化
CAINZをはじめとするホームセンターでは、特別な道具を準備しなくても、簡単に施工できる断熱アイテムが多く販売されています。
「カインズでは『DIY』を『日曜大工』のような休日に本腰を入れて取り組まなければならないものではなく、くらしをより自分らしくアレンジする創意工夫の精神と拡大解釈し、『くらしDIY』をブランドコンセプトにお客様のくらしをサポートしています。なので、特別な道具よりも『やる気』が必要でしょうかね」
宮田さんによれば、貼るタイプのアイテムも強粘着ではないため、賃貸住宅でも安心して使用できるといいますが、まっすぐ貼るのに慣れるために小窓などから試してみることをおすすめします。シールやテープで貼り付ける際には、貼り付ける場所の汚れや油分を取っておくのが綺麗に施工するポイントです。
省エネ住宅や住まいの断熱が注目されている昨今、断熱アイテムの売れ行きにも変化が見られているといいます。
「近年、断熱アイテムの需要は非常に高まっています。ここまでご紹介した住まいの断熱性能を高めるアイテムに加え、羽織れるブランケットや保温性のあるラグなど、いわゆる『あったかグッズ』の需要も全体的に上がっています。
断熱アイテムやあったかグッズの需要が高まり始めたのは、2021年ごろからです。電気代の高騰やエコ志向の高まりに加え、コロナ禍を経ておうち時間が長くなったことも影響しているのではないでしょうか」
「断熱ワークショップは、自治体や専門家の方などと一緒に開催させていただいているので不定期の開催ですが、木工などのワークショップは、店舗によってはお子さまと一緒に親子で参加できるDIYワークショップなどとして定期的に開催しています。お子さまをはじめ手が小さい・握る力が弱い方にも扱いやすいドリルドライバーなどの商品開発にも力を入れています。
また、店舗によっては、個人のお宅では揃えるのが難しい3Dプリンターやレーザー加工機などの設備を揃えている『カインズ工房』もあり、店舗でお買い求めいただいた商品の加工などにご利用いただけます。一部店舗では、工具のレンタルもしています」
ワークショップや工具レンタルは、とくにDIY初心者にはうれしいポイント。DIYのハードルがさらに下がりそうです。
DIYで手軽に断熱性UP
「断熱」というと、注文住宅やリフォームというイメージもあるかもしれませんが、DIYでも簡単に住まいの断熱性を高めることができます。
DIYは、商品選びから楽しめるのも魅力の1つ。自分自身で手を加えることで、住まいに愛着もわくはずです。ぜひ、お近くのホームセンターでも断熱グッズに着目してみてください。
SUUMOジャーナルから引用