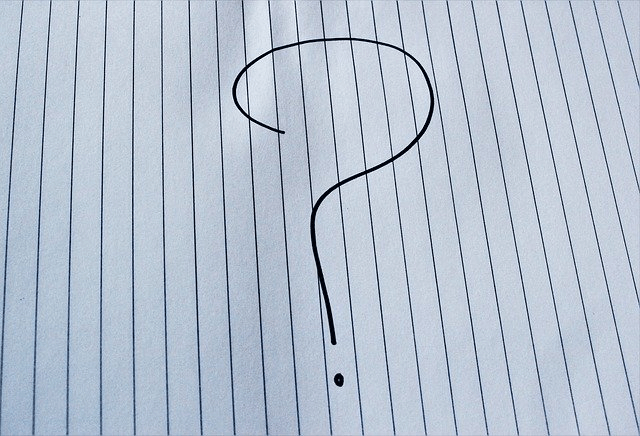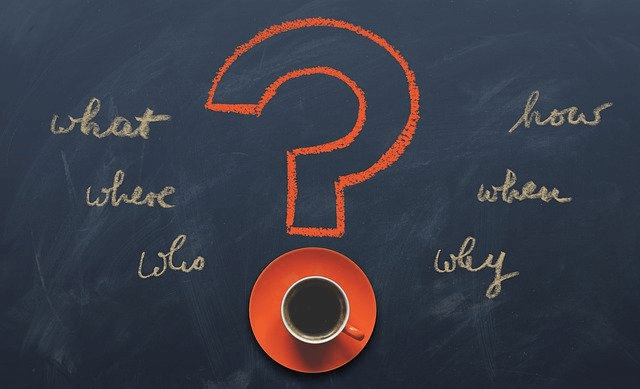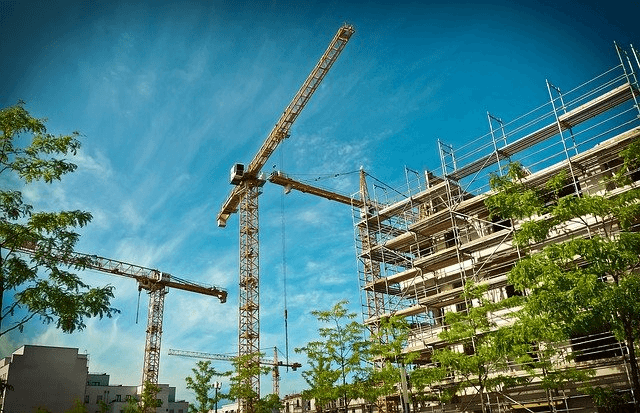建設業が今後取り組むべき課題
前述した今後の見通しを踏まえたうえで、建設業が取り組むべき課題について解説します。以下、3つのポイントが挙げられます。
①就業者数の減少と少子高齢化
まずは、人手不足を解消しなくてはなりません。
本記事の前半で述べたとおり、建設需要が増加している一方で、建設就業者の高齢化が進み、若手は少ないという現状です。
このまま若手人材を確保できなければ、今後に向けて技術承継ができず、事業の継続が難しくなると懸念されます。
これから建設業に入職する人を確保し、離職することなく長く働いてもらいながら着実にキャリアアップを図れるよう、働く人の処遇を改めて見直す必要があります。
②長時間労働
長時間労働の是正も必要です。
建設業の労働時間は、ほかの産業と比べて長い傾向にあります。
国土交通省の資料によると、年間の総実労働時間は全産業と比べて90時間長いことが明らかになっています。約20年前と比較すると、全産業では総労働時間が約90時間減少しているものの、建設業においては約50時間減と、減少幅が少ない点も懸念されます。
今後も長時間労働を改善できなければ、「建設業は業務負荷が高い」といったネガティブなイメージを払拭できず、若者離れがさらに進んでしまう恐れがあります。
③インボイス制度の導入による一人親方の負担増
2023年10月から「インボイス制度」が導入され、個人事業主として活動する一人親方の税負担が大きくなってしまう課題も挙げられます。
インボイス制度とは、商品・サービスの売り手(一人親方)が、買い手(取引のある建設関連企業)に対して、正確な適用税率や消費税額などを伝える制度です。
一人親方は、課税事業者(消費税の納付義務を負う)になるか、免税事業者(消費税の納付義務を負わない)のままでいるか、自身で選択できます。しかし、売り手側が消費税を国へ納付しなければ、その消費税額は取引先へ転嫁されることがあります。
そのため、買い手側の立場を考慮し、「インボイスに対応し、課税事業者になる」という選択をした一人親方も多いかもしれません。
すると、一人親方は消費税を納税する必要があり、これまでと比べて手元に残る金額が減ってしまうのです。
また、買い手側である建設関連企業の立場では、経理処理がこれまでよりも煩雑になります。
取引のある一人親方のインボイス対応状況を正確に把握しておかなくては、自社の経営に少なからず影響を及ぼすことになるでしょう。
4.建設業の課題解決に向けた対策

ここからは、建設業の課題解決に向けた対策を具体的に見ていきましょう。
①外国人材の活用
人材不足への対策として、外国人材の活用も有効です。
建設業に従事する特定技能外国人は年々増加しています。
特定技能とは、建設業をはじめとする人手不足とされる分野において、就労を可能とする在留資格のことを指します。
特定技能制度には「1号」と「2号」があります。1号の在留期間は通算5年であるのに対し、2号では在留期間の更新に上限がありません。2022年には、建設業において初の2号認定が出ています。
②ICT施工の導入
ICT施工の導入も有効です。ICT施工とは、工事現場で情報通信技術を活用し、作業員の負担を減らして生産性向上を図ることを指します。
ICT施工によって業務効率化が実現すると、人手不足の緩和、長時間労働の是正につながるでしょう。また、ICT建機の導入で稼働時間が減少した場合、その分のCO2排出量も減ると期待されています。
③若者と女性の採用
若者と女性の採用・定着に向けて取り組みを強化しましょう。
前述したとおり、建設業で働く若者の割合だけでなく、女性も少ない状況です。今後、新たに採用する人材を定着させるためには、若者や女性が働きやすく、長く働き続けられて、離職率の少ない職場づくりを目指す必要があります。
具体的には次のような、働き方改革関連の施策が推奨されます。
- 週休2日制の実施
- 出産・育児休暇取得
- 教育制度の充実
- 業務効率化による残業時間の削減
④建設キャリアアップシステムの導入
建設キャリアアップシステム(CCUS)を積極的に導入して利用しましょう。
建設キャリアアップシステム(CCUS)とは、建設業団体と国交省が官民一体で推進する新たな制度です。技能者の技術・経験を見える化し、業界全体の質の向上が目的です。
たとえば一人親方は、システムへの登録を無料でできて、資格・実績・スキルを可視化できます。保有技能を正当に評価され、より良い仕事の受注につながる可能性が高まります。
⑤サプライチェーン全体で建設資材の適切な価格転嫁を実施
建設に必要な主要資材の価格高騰が起こるなか、多くの建設企業は注文者(施主)に対して契約変更協議の申し出を行っているものの、契約変更が行われないケースも見られます。
そこで国土交通省は、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を図るよう、発注者と受注者間で必要な契約変更を実施できる環境を整備しました。
具体的には、以下のような取り組みによって、発注者・受注者としてそれぞれ取るべき行動が明確化されました。
- 契約締結状況のモニタリング調査を実施
- 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針の提示
受発注者の両方が、資材コスト・労務費上昇を適切に価格へ転嫁できるよう、互いに交渉や契約のあり方を見直す必要があります。
⑥施工管理アプリの活用
業務効率化を進めるために「施工管理アプリ」など、ITツールを積極的に活用しましょう。
施工管理アプリとは、現場関係者が必要な書類、図面、写真、各種資料やデータなどを、アプリ上で一元管理し、パソコンやスマートフォン、タブレットからでも手軽にアクセスできるようにするツールです。
たとえば、資料共有機能を活用して、書類や図面、写真など、外出先からでもアクセスできる状態を整えておくことで、現場と事務所を往復する手間がなくなり、業務効率化が実現するでしょう。
また、チャット機能を搭載した製品もあるので、現場関係者間のコミュニケーション活性化、若手とベテラン間での情報共有促進など、さまざまなメリットを期待できます。